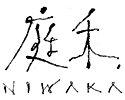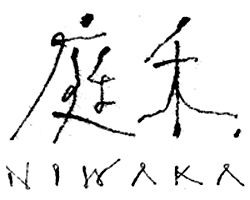カタクリに日がよく当たるようにと、工房名月の裏の山では
ここのところ間伐作業が行われています。
その話を工房名月のなっちゃんが最近お知り合いになった、
宮大工もされていたことのある楽器職人の岡田さんにお話ししたら、
丸太挽きをやってみよう!ということになり、丸太挽きって?と思いながら、いざ丸太挽き。
まずは山から木を引っ張っておろします。木って、とても重いのですね!
岡田さんがやってみたかったという皮剥き。
するすると剥けてのぞいた木肌からは、爽やかですっとしたいい香りが立ち上ります。
瑞々しいその木肌を舐めてみたら、淡い甘さ。ちょっとサトウキビにも似ているでしょうか。
じゃーん!ちゃんと乾かせば、この皮で屋根を葺いたりできるのだとか。
ここから見たこともない形と大きさの鋸が続々登場。
私も参戦しましたが、この鋸を挽く動きはものすごくハード。体幹がすごく鍛えられそうです。
ちなみに私は、この日から1週間、疲労感が抜けませんでした・・・・。
ここからは割り作業。杭を打ち込み、木の繊維に沿って自然に割ります。
こうすると狂いの少ない材になるのだとか。
一日で全部はできなかったけれど、
2本のうち、1本は柱材、1本は板材用に製材作業をしました。
材木は、山に立っていた木からできている。
そのことを、私は分かっていなかったと、今回思いました。
そして、材木はなんと貴重なものかとも思います。
大事に大事に使うべきものです。
いつか敷地内に小屋を建てたいと思っているので、
敷地内の山の木で建てられたらどんなに素敵だろうと、夢は膨らむばかり。
ほんとうに貴重な体験をさせていただいたし、すごくすごくおもしろかったです。
長い時間のなかで引き継がれてきた、人間の知恵と技を垣間見た気がします。
あの木の香りと淡い甘さが忘れられません。
ミシミシッという音とともに裂けた木。繊維でできているのがよくわかります。