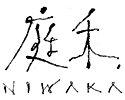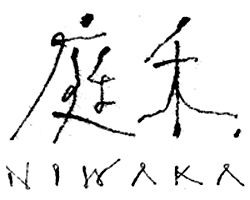今年も6月に瀬戸で開催されたやきものフェア、『ユノネホウボウ2015』。
今年も私は実行委員をしておりまして、
関係者打上げをここ山水ラボラトリーで行うこととなりました。
夕方に実行委員やボランティアスタッフさんの方々が集まってきて、
バーベキューに窯焼きピザ、燻製・・・と、煙出し放題なここならではのメニューが一揃い。
そして今回とても楽しみだったのが、楽焼き体験。
代表をしている安達健さんの指揮のもと、
即席の窯に火が入れられ、素焼き済みの素地に釉薬をかけるところから始めました。
実は私、やきものが作られるプロセスを目にするのは生まれて初めて。
終始、「はー、こうやってやってるんだ。へー。ははー。」と私は驚くこと、感心することばかり。
釉薬をかけます。
作家さんたちに聞けば聞くほど、
テストを繰り返し、その結果をもとに出来上がりを想像しながらかけていくのだとうことに驚くばかり。
私もやらせてもらいましたが、いったいこれがどんなことになるのかまったく想像ができません。
目の前に出来上がりが見えないのだ、というそのことに「うー、そうなのかー」と唸ってしまう。
で、焼きます。
ボランティアスタッフの方々には、やきものをこれからやっていこうと目指して学校に通ったりしている方も多く、
安達さんのレクチャーを真剣に聞いていました。
いやあ、これはきっと貴重な体験になるんでしょうね。
実演。焼きあがった器を籾殻の中に入れる燻し。
やきものってこんなに真っ赤っ赤なの?!知らなかった!!
ぶわっと上がる煙。燃える籾殻。なんというか野性的な様子に興奮興奮!
この燻しで生地が黒くなったり、貫入に黒い色が入ったりするのだとか。埋める具合でそのつき方が変わるのです。
で、このあと水にじゅわっーと浸ける急冷。真っ赤なやきものがみるみるうちに冷めていく。
すると仕上がりが見えていきます。
ええっ?!こんなことになるのか!と、もうほんとうに驚くというかなんというか。
やきもの。使うのは大好きだけれど、どうやってできているのか私はなんにも知らなかった。
想像さえしてみたことがなかったかもしれない。
楽焼きは初めてという作家さん達がいたから、きっとまた特殊なものなのだろうけれど、
けれど、焼きあがるまでわからない、
造形、釉薬、温度、窯の性質・・・と、試して試して、やっとそれぞれのやきものになっているのだろうことは
どんな作り方だろうときっと同じで、
そのことを恥ずかしながら、私は初めて知った、と思いました。(いや、それでもほんの一部を、なんだろう。)
これが出来上がった楽焼き。
真っ暗のなか、火を囲んで焼き上がりを待ち、煙と湯気があがってやきものができる。
楽しかった。おもしろかった。興奮しました。
もうそればかりです。
安達さん、どうもありがとう。これから器を使うときの心もちが、ぐっと変わる気がしています。
ユノネホウボウの関係者の皆さん、今年もどうもありがとうございました!